松尾大社 詳細情報 口コミ・レビュー一覧
名称
松尾大社
施設説明
松尾大社は、京都市西京区嵐山宮町にある神社。式内社で、二十二社の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。
所在地
〒616-0024 京都府京都市西京区嵐山宮町3
営業時間
月曜日: 9時00分~16時00分
火曜日: 9時00分~16時00分
水曜日: 9時00分~16時00分
木曜日: 9時00分~16時00分
金曜日: 9時00分~16時00分
土曜日: 9時00分~16時00分
日曜日: 9時00分~16時00分
火曜日: 9時00分~16時00分
水曜日: 9時00分~16時00分
木曜日: 9時00分~16時00分
金曜日: 9時00分~16時00分
土曜日: 9時00分~16時00分
日曜日: 9時00分~16時00分
電話番号
レビュー件数
4,073
注目キーワード
価格帯
※当施設情報は2026年1月2日現在にGoogleMAP上で表示されている情報を基に更新しております
ランキング推移
レビュー投稿
レビュー一覧
当サイトでは各施設に投稿されている可能性のある『荒らしや悪質なコメント』を排除する目的で、星評価1に相当する個別レビューは掲載しておりません。但し、星評価1が投稿された場合は『件数としてはカウント』して当サイト独自評点を算出しております。予めご承知おきくださいませ。
投稿日:9ヶ月前
京都の名勝嵐山歩近くに坐します松尾大社さま酒造会社さんの清水を戴かれて1年の銘酒が出来上がりますょうにと、日本全国の酒造会社が祓い清めに詣られてございます、酒造りには豊富清水が負ければ銘酒は造れない途の事で在るらしいと聞かされました、又水も
0
松尾大社がランキングされている他のオススメ記事
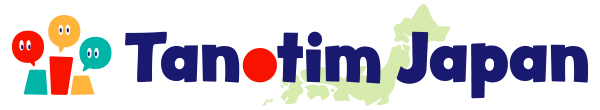
木が生い茂って岩があるので、自然の中にある印象が非常に強いです。
広い敷地内を歩いていると、不思議な力を感じるので、心が静まっていきます。
境内には酒樽が数多く並